入社してまだ1年も経たないうちに、「もう辞めたい」と感じるのは、決して珍しいことではありません。
仕事や職場環境に期待していたことと現実のギャップが大きいと、日々のやる気が削がれ、転職を考え始めるのは自然な流れです。とはいえ、勢いだけで辞めてしまうと、後悔につながるリスクもあります。
そこで本記事では、新卒1年以内に辞めたいと感じたときの判断基準や注意点、そして第二新卒として転職を有利に進めるための具体的な方法を、経験やデータを交えて解説します。
新卒1年以内で「辞めたい」と感じるのは珍しくない
入社後まもない時期に辞めたいと感じる人は、想像以上に多くいます。
特に最初の1年は、慣れない環境や責任の増加、職場の人間関係など、ストレスの原因が集中する時期です。
厚生労働省データで見る離職率
厚生労働省の調査によれば、大学卒業後に就職した人の12.3%が1年以内に離職しています。高卒就職者の場合だと16.7%です。
なお、3年以内までみると大卒就職者は34.9%、高卒就職者は38.4%が離職しています。さらに、いずれも上昇傾向です。
こうした実データからも、1年以内に辞めたいと思うことは決して例外ではないことがわかります。
筆者の前職でも、新卒者が1年以内に辞めるケースは散見されました。経験則ですが、およそ10~15%といったところですので、厚生労働省のデータとも一致します。
参考:
新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)|厚生労働省
別紙1:新規学卒就職者の学歴別就職後3年以内離職率の推移|厚生労働省
よくある辞めたい理由
新卒1年以内の離職希望者からよく聞かれる理由には、以下があります。
- 人間関係のストレス(上司や同僚との相性、ハラスメントなど)
- 労働時間・残業が多すぎる
- 給与や待遇が期待より低い
- 仕事内容が希望や適性と合わない
- 企業文化や社風が合わない
これらの要因は複数重なることが多く、結果として早期離職の引き金となります。
心理的負担が大きい理由
社会人1年目は、学生時代の自由度の高い生活から一変し、組織の中での役割や責任を急激に求められます。慣れない業務や評価制度への不安、成果を求められるプレッシャーは、精神的に大きな負担となります。
筆者も新卒1年目のとき、周囲との比較や自己評価の低さから「このままでいいのか」と悩んだ経験があります。
今すぐ辞めるべきか、もう少し様子を見るべきかの判断基準
辞める決断は一度きりです。だからこそ、感情だけで動くのではなく、冷静に状況を判断することが重要です。
辞めた方がいいサイン
以下のような場合は、早期に辞めることも検討すべきです。
- 長時間労働や休日出勤が常態化しており、改善の兆しがない
- 心身の健康に影響が出ている(不眠、体調不良、うつ症状など)
- パワハラやセクハラなどのハラスメントが放置されている
このような環境に身を置き続けることは、キャリアだけでなく人生全体に悪影響を与える可能性があります。
まだ様子を見てもいいケース
一方で、状況が一時的なものである場合は、少し時間を置くことで改善する可能性もあります。
- 繁忙期が終われば業務量が落ち着く
- 上司やチームメンバーの異動が控えている
- 配属替えや業務内容の変更が予定されている
短期的な不満と長期的な成長機会を天秤にかけ、冷静に判断しましょう。
判断に迷ったときの「棚卸し」方法
紙やPCに「仕事内容」「人間関係」「待遇」「将来性」などの項目を作り、それぞれに満足度を書き出してみましょう。視覚的に整理することで、感情に流されず客観的に判断できます。
この方法は、筆者が転職相談を受けるときによく提案しています。感情の整理と優先順位付けに効果的です。これをするだけでも、明確に心が軽くなるのでおすすめです。
「新卒1年以内で辞めたら後悔する」ケースとは
退職や転職は大きな決断です。焦って行動すると、次の職場でまた同じ失敗を繰り返す可能性があります。
次の職場選びで失敗するケース
同じ業界・同じ働き方の企業に転職してしまい、結局同じ理由で辞めたくなるパターンがあります。前職での不満点を明確にし、それを解消できる環境かを見極めることが大切です。
転職先のリサーチ不足
面接時の印象や給与条件だけで判断し、入社後に「思っていたのと違う」と感じるケースは少なくありません。企業の口コミサイトやOB/OG訪問など、多角的な情報収集が必要です。
「逃げの転職」と見なされる状況
面接で転職理由を説明できない場合、「ただ逃げただけ」という印象を持たれ、選考で不利になることがあります。短期離職の場合は特に、前向きな理由への言い換えが重要です。
実は第二新卒は転職市場で有利
新卒1年以内で辞めても、第二新卒というポジションを活かせば転職市場で有利に立ち回れます。
第二新卒の定義と市場価値
第二新卒とは、一般的に「学校卒業後、1〜3年程度の社会人経験がある人」を指します。企業は第二新卒に対して「若さ」と「社会人としての基礎」を期待しており、即戦力よりも伸びしろを重視する傾向があります。
新卒就活より難度が低いと言われる理由
新卒採用のように一斉エントリーや限られた選考期間がないため、応募のタイミングが自由です。また、実際に社会人として働いた経験が評価されるため、書類や面接での説得力が増します。
有利に進めるためのポイント
- 在職中に転職活動を始めることで、選択肢を広げやすい
- 職務経歴書には成果や工夫した点を具体的に記載する
- 面接では「早期離職の理由」を前向きに変換して伝える
これらを押さえることで、短期離職の不利を最小限に抑えられます。
辞める前にやっておくべきこと
新卒1年以内の退職は、その後のキャリアや市場での評価に直結します。どのような形で転職活動を始めるにしても、事前の準備が成功のカギです。ここでは2つのパターンに分けて解説します。
可能な限り「次の入社先が決まってから」辞める
最もリスクの少ない方法は、在職中に転職活動を進め、内定を得てから退職することです。
この場合のメリットは大きく、特に以下の点で有利になります。
- 収入が途切れないため生活の安定を保てる
- 精神的余裕を持って求人を選べる
- 採用側から「計画性がある」と評価されやすい
具体的な準備としては、まず転職市場での自分の立ち位置を把握することが重要です。
仕事の強みや適職を9タイプに分類してくれる「適職診断(Re就活)」は、自己分析や職務経歴書の作成にも役立ちます。約3分でできて意外と面白いので、一度やってみる価値はあります。

また、履歴書や職務経歴書は在職中から少しずつ更新し、業務の中で工夫した点や成果をエピソードとして記録しておくと、面接での説得力が増します。
辞めてから転職活動をしたい場合
心身の負担が限界に達している、環境がどうしても合わないといった場合は、やむを得ず退職後に転職活動を始める選択もあります。
ただし、この場合は生活や活動計画をしっかり立てておかないと、焦りから不本意な企業に入社してしまうリスクが高まります。
特に意識したい準備は次の通りです。
- 生活資金の確保
目安として3〜6か月分の生活費を準備しておくことが理想です。 - 失業給付の条件確認
雇用保険の加入期間や退職理由によって給付条件が異なるため、事前にハローワークで確認しましょう。 - 退職後のスケジュール作成
いつまでに応募、面接、内定を目指すかなど、活動期間を明確にしておくことで無駄な時間を減らせます。
このパターンでは、自由に時間を使える一方で収入が途切れるため、金銭的・精神的な備えが重要です。
「辞めてよかった」・「後悔した」事例
経験者の事例は、自分の判断に役立つ重要なヒントになります。ここでは、実際に筆者が見聞きしたケースを簡潔に紹介します。
辞めてよかった事例
- キャリアチェンジが成功した
前職では営業職だったが、興味のあったIT業界に転職。研修制度の充実した企業に出会い、スキルアップと年収増を同時に実現。 - 健康を取り戻せた
長時間労働と休日出勤で体調を崩していたが、転職後は労働時間が改善し、生活の質が向上。
いずれも、辞める前にしっかりと転職先の情報を収集し、自分の希望条件を明確にしていた点が成功の鍵となっています。
後悔した事例
- 転職先が合わず短期離職を繰り返した
勢いで辞めて、十分なリサーチをせずに入社。結果として再び同じ不満に直面。 - 生活資金の準備不足で妥協した
貯金が尽きる前に就職しようと焦り、条件面で不満のある企業に入社。
後悔したケースでは、「情報不足」と「準備不足」が共通の要因です。
後悔しないための転職活動ステップ
新卒1年以内の転職でも、戦略を持って動けば十分成功が可能です。
目標設定と条件の優先順位付け
「年収」「勤務地」「仕事内容」「社風」など、自分が譲れない条件を3つ程度に絞り、優先順位を決めましょう。全ての条件を満たす企業は少ないため、あらかじめ取捨選択をしておくことで後悔を減らせます。
情報源の選び方
求人票だけではわからない情報も多いため、企業口コミサイトやOB/OG訪問、説明会など複数の情報源を活用しましょう。
特に職場の雰囲気や残業時間などは、現役社員や元社員からの情報が有効です。
面接対策と退職理由の説明方法
短期離職の場合、必ず理由を聞かれます。
ネガティブな理由をそのまま話すのではなく、「新しい環境でこういうことを実現したい」という前向きな動機に変換しましょう。
例:「前職では顧客対応が中心だったが、自分の強みを活かして企画業務に挑戦したいと考えたため」など。
まとめ
- 新卒1年以内で辞めたいと思うのは珍しくない
- 感情だけで判断せず、冷静な状況分析と準備が必要
- 第二新卒は転職市場で有利だが、情報収集と戦略的行動が欠かせない
- 辞める前の準備が、転職の成功と後悔回避の分かれ目になる
迷っている時間は、自分を見つめ直すチャンスでもあります。焦らず準備を整えてから動くことで、納得できる選択ができるはずです。
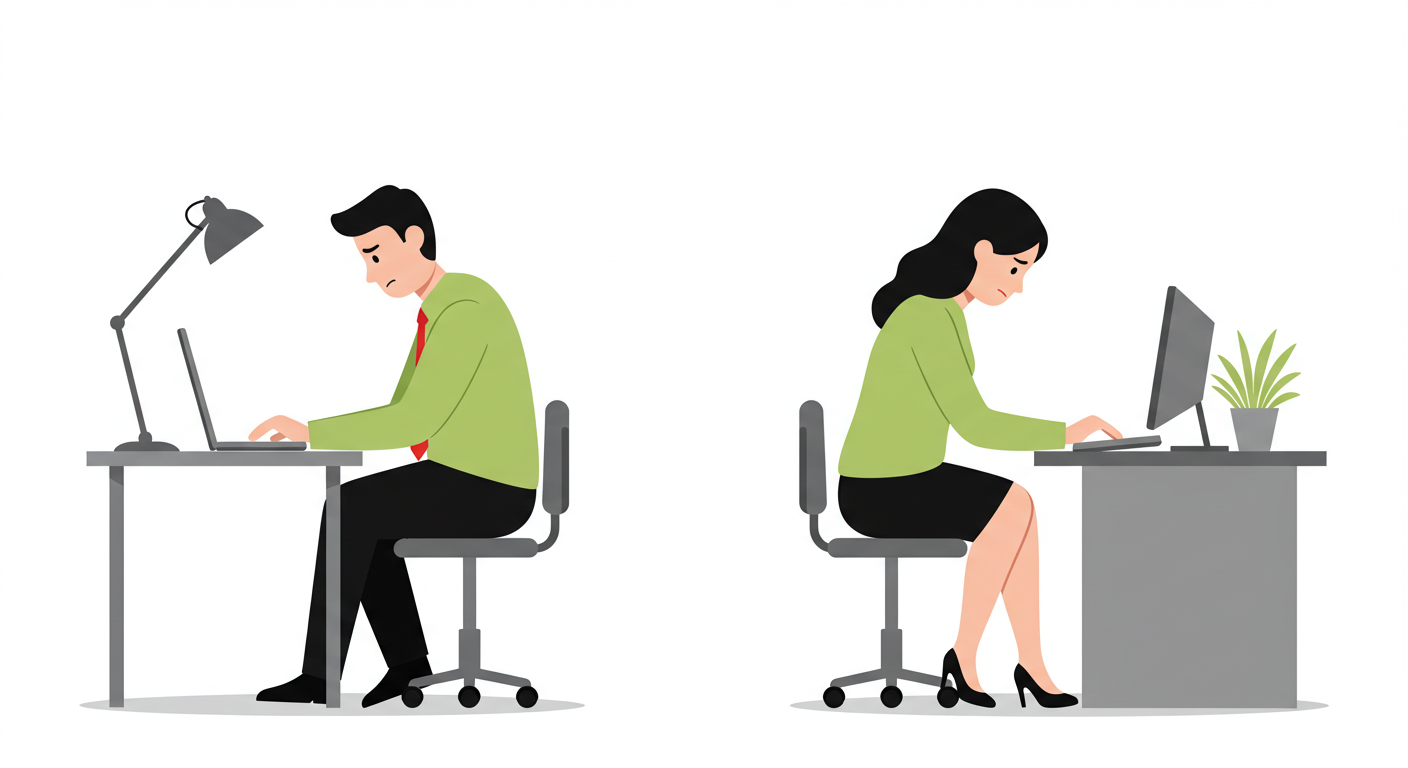


コメント